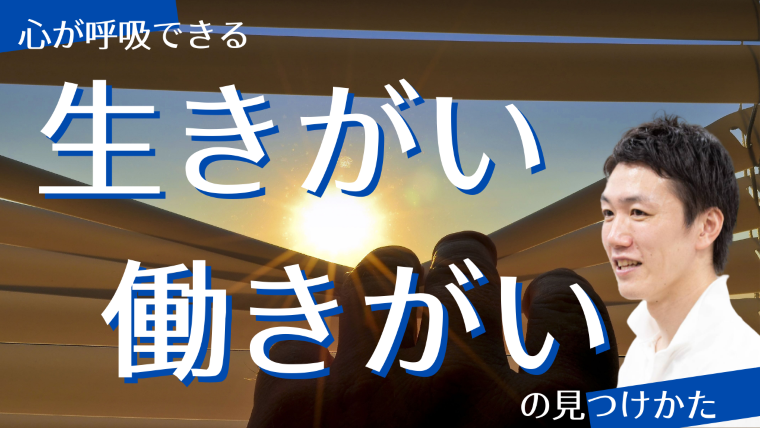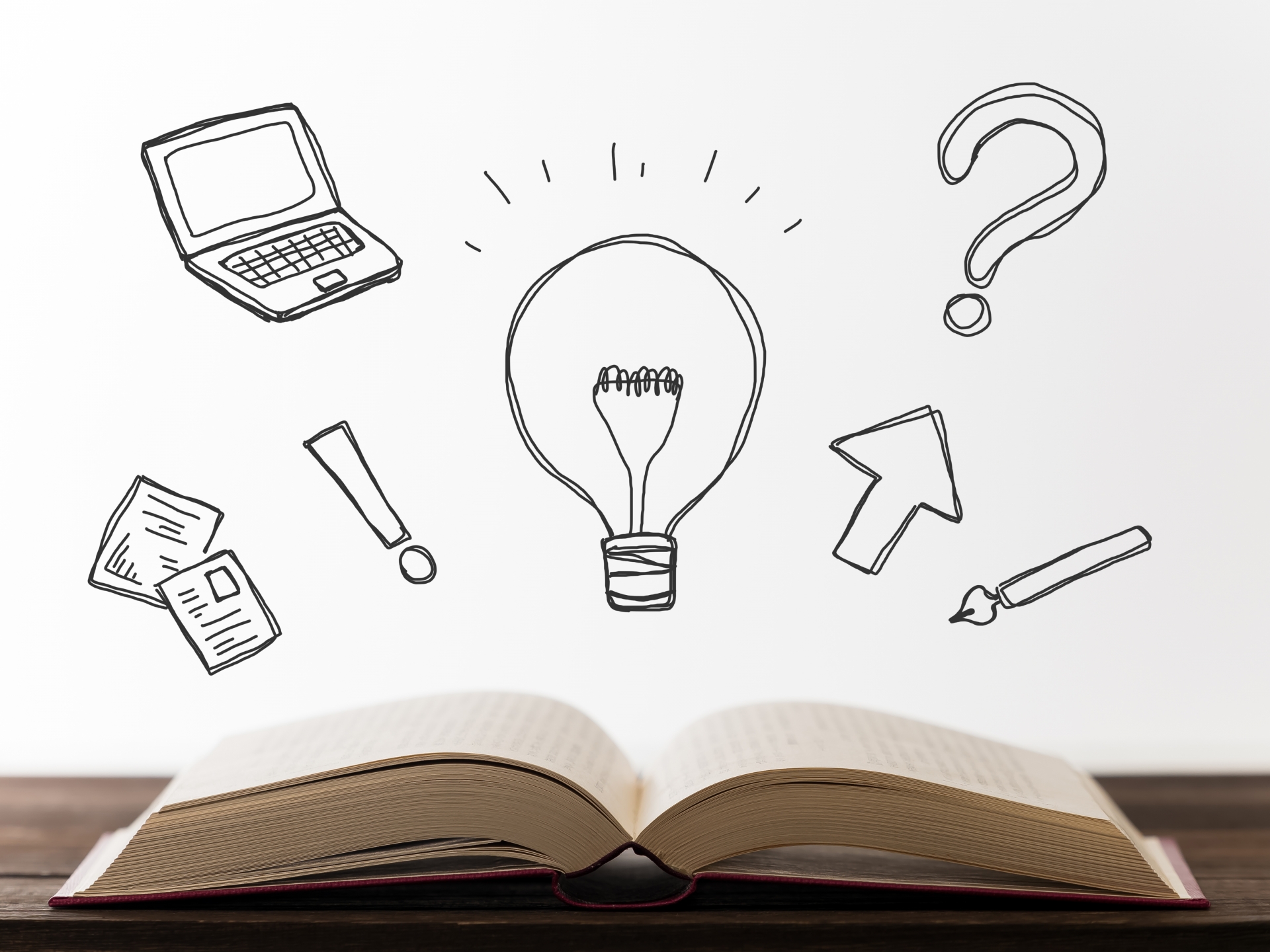PC初心者の私がプログラミングを学ぼうと思ったわけ
①PC初心者の私がプログラミングを学ぼうと思ったわけ 初心者がプログラミングを学ぶ時に挫折するポイントや、こうして学んだらいいというような記事を多く目にしますが、この記事では全く違う観点で書いていきます。なぜなら、私が学んだプログラミングが一般にあるプログラミング教室とは違うからです。 普通プログラミング教室に通う目的としては、何かのアプリを作成したいとか仕事で必要、転職に役立つなどの現実の生活に+αする為ということが多いかと思います。けれど私が学んだプログラミングはデジタルリーダーシッププログラムという教育プログラムの中で学ぶもので、プログラミングの他にPCに関する全般を学ぶものでした。プログラミングを学ぶことで、宇宙の成り立つ仕組みも理解できるという最新のIT教育です。+αではなくて全てを0化したところから新たに創りだしていく+∞の学びです。 ここでプログラミングを学ぶことで、PCの画面を創りだすことと自分が見ている現実という画面を創りだすことが同じ仕組み、同じアルゴリズムであることを認識できます。ITに心が入った教育ができるのです。自分の見ている現実がPCと同じアルゴリズムであると言われても、そもそもPCが良くわかっていない私にとって、同じだと受け取り切れないモヤモヤもあり、「知りたい!」という欲求が強くなっていきました。なので、プログラミングを学んでスキルを身につけたいわけではなく、原理を理解したかったのです。それにはこのデジタルリーダーシップが最適でした。 ということで私の主観によるところもありますが、プログラミングを学ぶときに苦しんだポイントを書いていこうと思います。 ②その前に、現在のプログラミング市場 2020年に小学校にプログラミング教育が導入されたこともあり、子ども向けのプログラミング教室の市場は2013年に約6.6億、2018年に約90億、2023年には約226億の予想がでていて、10年で約35倍の伸び率になっています。 また大人もリカルレント教育(生涯にわたって教育と就労のサイクルを繰り返す教育制度)として、プログラミング教育の需要が拡大しています。こちらは詳しい数字は調べることができなかったのですが、最近のIT事情としてDX(デジタルトランスフォーメーション)という単語を耳にすることが増えてきていませんか? DXとはデジタル技術による業務の改革やビジネスの変革のことですが、IT後進国と言われている今の日本としては、ITに関しての知識があるかないかで、社会のとらえ方・活躍の場が違ってくるのではないかと思います。 不思議なのは、小学校にプログラミング教育が導入されることになって、子どものプログラミング教室の需要は増したけれど、その親であるお父さん、お母さんがプログラミングを一緒に学んでみようとか、自分も知っておきたいという意識にあまりならないことです。3700人の保護者を対象に行ったアンケートでも、53%の人が「親の自分が理解できるか不安」という回答があるそうです。 [...]