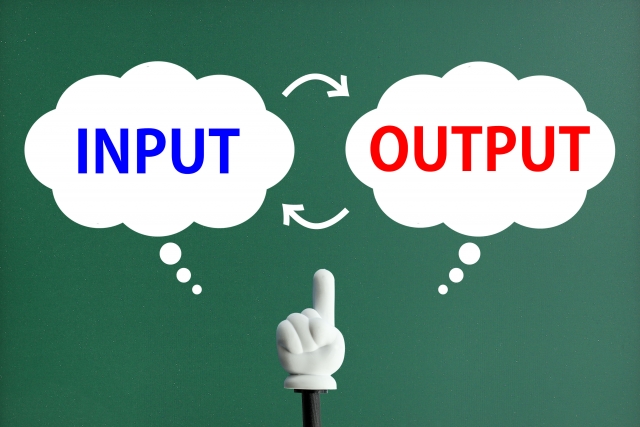出来ることが増えるほど虚しい。その理由と関係主義の可能性
こんにちは。JeiGrid株式会社 広報担当の塩田です。 ブログをご覧頂きありがとうございます。私はプロジェクトを回していく中で、疑問に浮かぶことがありました。 それは「なんでできることが増えて 効率的に成果を出せるようになればなるほど こんなに虚しくなっていくのだろうか」と。 「いやいや、業務を遂行する上で結果を出すことはいいことだしみんなの役に立っているしそれで十分じゃないか」と自分を言い聞かせるものの言いようもない孤独感がじんわり襲ってくるような、そんな感覚。 仕事をしながらもこの疑問に向き合ったときに、大きく自分の中で変化したことがありました。この気づきを仲間に伝えたところ、「その感覚、すごく分かる」と共感してもらえることも多かったので今回はそのことを私なりに紐解いていきたいと思います。 [...]